主役はエンジニア。プロジェクトマネージャーが伴走して、技術を価値につなげる
Nature Architectsでは、エンジニアとプロジェクトマネージャーが密に連携しながらプロジェクトを進めています。エンジニアが技術に集中できるように、プロジェクトマネージャーは隣で伴走しながら、チーム全体を前に進める役割を担っています。今回は、そんなふたりがどんなふうに関わり合い、どんな思いで価値を生み出しているのか。現場のリアルなやりとりを通して、その関係性や仕事の魅力に迫ります。
PROFILE

●永澤正和
2024年入社
早稲田大学院建築構造学卒業後、ブリヂストンにて振動技術の研究開発・品質経営・新規事業開発に従事。その後、シグマクシスにて経営戦略策定・工場DX・経営人材育成・PMO支援を実施。3児のパパ。

●躍場 由記
2024年入社
大学院で機械工学の修士号を取得後、電機メーカーで10年間、産業機器の機構設計および先行開発に従事。
Page Index
直接エンジニアが向き合うことが顧客の満足度に

Nature Architectsではどのようにプロジェクトが進行しているのでしょうか。
永澤:クライアントとの対話から課題を明確にし、仮説を立てるところから始まります。仮説が合意できたらプロジェクトが正式に立ち上がり、エンジニアが合流。具体的な検証フェーズに入ります。
プロジェクト前半は主に仮説検証、後半は「どのようにしてその価値を産み出せたか」を明らかに。最終的にクライアントと成果を共有し、生み出した価値に合意してプロジェクトが完了します。
プロジェクト完了後は、プロジェクトの残課題を引き継いだり、類似課題への適用の提案を提案展開したりすることもあります。
躍場:Nature Architectsでは「技術そのものが事業の核」のため、エンジニアが直接、クライアントと話す機会が非常に多いと思います。
物理現象にもとづく解析の意図や過程をエンジニアが話すことで説得力が増し、クライアントともより深い信頼関係が築けます。打ち合わせには、先方も技術者が同席するケースが多いので、技術的な議論が深まることで、クライアントの満足度も高くなっている印象です。
クライアントとの関係構築で大切にしていることはありますか。
永澤:やはり「価値を共に創る」というスタンスですね。クライアント技術者に対して当社エンジニアが、クライアント意思決定層に対しては当社PMが、という役割の住み分けを意識して、全体として価値が伝わる構造をつくります。
躍場:クライアントからの難しい要求に対しても、PMと「どうすればそのリクエストを実現して価値に変えられるか」を徹底的に議論します。単純に「できない」と突っぱねるのではなく、代替案を模索したり、納得のいく落とし所を探ったりする姿勢を大切にしています。
永澤:私たちのミッションは、クライアントにどれだけ「価値」を提供できるか。価値というと、お金や成果のような見えるものを想像しがちです。しかし、私たちの目指すのは、もっと本質的な「なぜそれをやるのか」という問いに応えることにあります。
技術はそのための手段であって、目的ではありません。しかし、技術という手段がなければ何も動かないのも事実です。だからこそ、どこまで深く掘り下げて、手段である技術に意味を持たせるかが重要だと思っています。
PMとエンジニアだけでなく、エンジニア同士も密に連携

チーム内での連携はどのように行われているのでしょう。
躍場:プロジェクトの内容や状況にもよりますが、基本的に週1回程度のミーティングに加えて、必要に応じて都度打ち合わせをします。佳境の時は1日に何度もやり取りすることもありますね。
普段から何気ない会話も多いので、雑談からプロジェクトに関する議論に発展することも多いですね。
永澤:PMとしてエンジニアが何を考えているのか、困っていることがないか、しっかり把握できるよう、普段から積極的にコミュニケーションをとるようにしています。
解析結果が出る瞬間などは、私自身もワックワクしながら待っているので、「結果が出たらすぐ教えてね!」と連絡したりもしていますね(笑)。
リーダーシップや役割分担についてはどうでしょうか。
永澤:役職や肩書きでリーダーが決まることはなく、「誰が一番その課題に向き合っているか」が重要です。例えば、エンジニアが提案の起点になることも多いですね。しかも、その提案に対して、自然とみんなが「やってみよう!」と協力し役割が決まっていきます。
─ プロジェクトの壁を超えたエンジニア同士のコミュニケーションも活発そうですが。
躍場:Nature Architectsには、社内コミュニケーションツールの中にメンバーが自分の興味があることや困りごとを自由に発信するつぶやきチャンネルがあります。社内SNSのようなものです。誰かがつぶやくとそれにコメントが集まり、自然発生的に技術的な議論になっていったりしています。
例えばあるプロジェクトで普段関わりのない材料(仮:玉子焼き)を扱うと社内展開したら、その力学特性の論文についてプロジェクト外のメンバーが調べて共有してくださり、そこから真剣な技術談議に発展したことも。自分には一見関係ない話題でも、「つぶやき」をきっかけに社内全員で意見交換して技術的な探求が始まるのがNature Architectsらしいところです。
永澤:エンジニアは週1で定例会議もやっていますよね。
躍場:そうですね。技術的に困っていることがあると定例会で共有して、ほかのエンジニアからアドバイスをもらったりもします。バッググラウンドが違うエンジニアが集まっているので、新しい視点を持てたりその場で解決することも多いです。またエンジニアだけでなく、事業開発メンバーの持つ知見が解決につながることもあります。全員で問題を共有しながら技術を深めていく文化がしっかり根付いているのを感じます。
「最近どうですか?」みたいな雑談も多いですし、そこからいつの間にか「そういえばこの件、こういうやり方もあるかも?」という議論になっていたりすることもあります。
しかも、決して否定から入ることがなく、まずは「聞いてみよう」「試してみよう」というスタンスです。自分の小さな問いかけが、チームの議論を動かすこともあって、そこが面白みにもなっています。
永澤:職種を超えた社内のコミュニケーションも活発だとよく感じています。オフィスには常におもちゃが置いてあり、難しいパズルを単に楽しむだけのこともあります。私を含め数名がジャイロ効果を利用して手首を鍛えるおもちゃ?にはまっていました(笑)。一方、面白い機構があると、よく変形自由度や論理を含む構造特性などの議論に発展したりします。このコミュニケーションがプロジェクトを超えて新たなアイデア提案につながっていたりします。
伝わってこそ、技術が初めて価値になる

Nature Architectsで働くことで、自分の成長を感じる点はありますか。
永澤:私は前職がエンジニアだったのですが、当時は「技術さえやっていればいい」という感覚があったのは否めません。しかし、Nature Architectsに来て、技術を価値に変えるための「伝え方」や「パッケージング」も重要であると感じています。
以前、あるプロジェクトで提示した解析結果を最初は受け入れてもらえなかったことがありました。原因は、技術的には正しく結果を導いていても、クライアントに「どのような着想で解析条件を組んだか、なぜこの解析条件だと結果が導けるのか、またなぜこの解析結果がクライアントにとっての価値となるか」を伝えきれなかったことにあったのです。
この経験から、技術の価値は「伝わってこそ初めて価値になる」と痛感。技術そのものだけでなく、それをどうクライアントに見せて届けるかを強く意識するようになりました。
躍場:私も入社当初は、自分の専門領域をどう発揮するかが大事だと思っていました。しかし、実際にプロジェクトを経験するうちに、改めてチームでの役割を意識することやクライアントへの伝え方も重要だと認識しました。技術的な部分だけでなく、プロジェクト全体にどう貢献していくかを常に意識するようになったと思います。
目の前の課題に向き合い、価値を創造する醍醐味

今後はどんなプロジェクトに関わってみたいと考えていますか?
永澤:私はこれまで製造業を担当することが多かったのですが、今後は衣料や環境分野の仕事もぜひやってみたいですね。Nature Architectsには、「あらゆる製造業を設計から革新する。」という大きなビジョンがあります。自分たちの設計技術がどこまで通用するのか、もっといろいろな分野でチャレンジしたいと思っています。
躍場:私は「設計できる対象」をもっと広げられたらいいですね。材料・構造・流体などの全てが絡み合う複雑なテーマに向き合ってみたいです。
例えば宇宙開発といったダイナミックなプロジェクトにぜひ挑戦できたらうれしいですね。しかも、それを自分一人ではなく、異なるバックグラウンドを持つ仲間たちと設計することができたらと想像すると、すごくワクワクします。
永澤:そういったスケールの大きな仕事も、最初の一歩は、目の前の課題に向き合うことから始まりますよね。そこをちゃんと積み上げていけるのが、Nature Architectsのチームの強さだと思います。
改めてNature Architectsで働く魅力を聞かせてもらえますか。
躍場:ずばり「世の中にまだ存在しないものを形にできる環境がある」ことですね。難しい課題に挑んで新しい技術や価値を創造するプロセスは、本当に刺激的です。最先端のツールや解析を駆使して「今までにない答えを出す」ことに、日々やりがいとワクワクを感じています。
永澤:エンジニアが主役になれる場を整え、クライアントに価値を感じてもらえるゴールを描く。それがNature Architects のPMの醍醐味です。PMとして、元エンジニアとして「技術を価値に変える」ことの難しさとその分のやりがいを感じられることが、充実感につながっています。
「わからない」を楽しみ、技術で届ける熱意を持つ仲間を
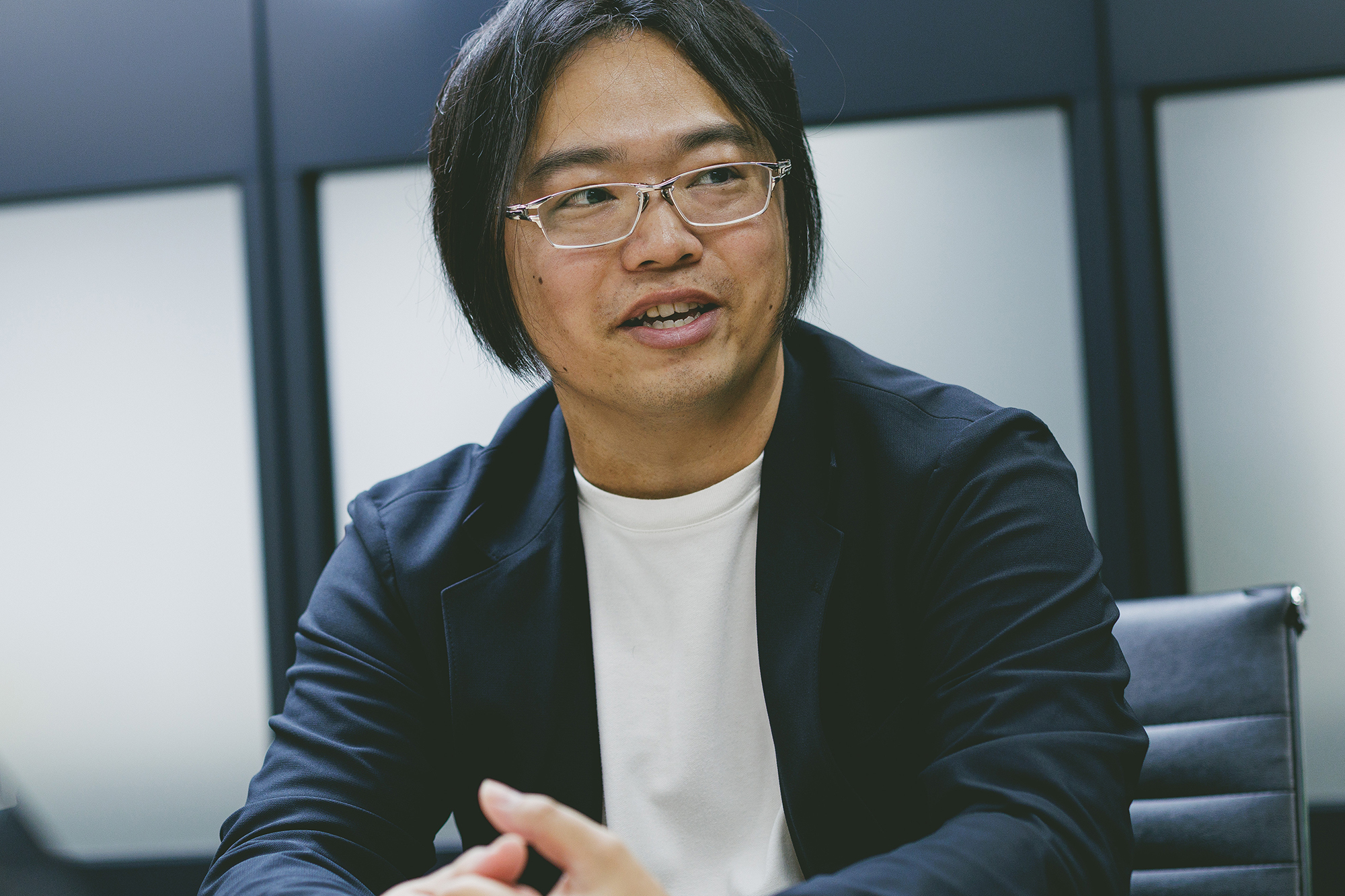
最後にどんな人と一緒に働いてみたいかを教えてください。
躍場:ひと言でいうと「わからないことを楽しめる人」です。Nature Architectsの仕事は、前例のないことに挑戦する連続です。「なんだこれ?」と思える好奇心を持ち、自分ごととして面白がれる人に仲間になってほしいですね。
学び続ける姿勢ももちろん必要です。幅広い技術領域や最先端の技術を扱うからこそ、知識のアップデートへの貪欲さも大切にしてもらいたいと思います。
永澤:Nature Architectsは「技術が好き」「ものづくりが好き」という気持ちを大切にしています。そして、その好きな技術を「誰かの役に立つ価値」として形にするのが我々の仕事です。
事業開発/PMとしては、すべての技術を理解するのは難しいですが、「技術の力で価値を生みたい」という強い意志を持っている人でいてほしいですね。そして、その技術を「よくわからないけどいい」で終わらせず、自分やクライアントが理解できるようわかりやすく伝えようと心を砕ける人と、ぜひ一緒に働けたらと思っています。







