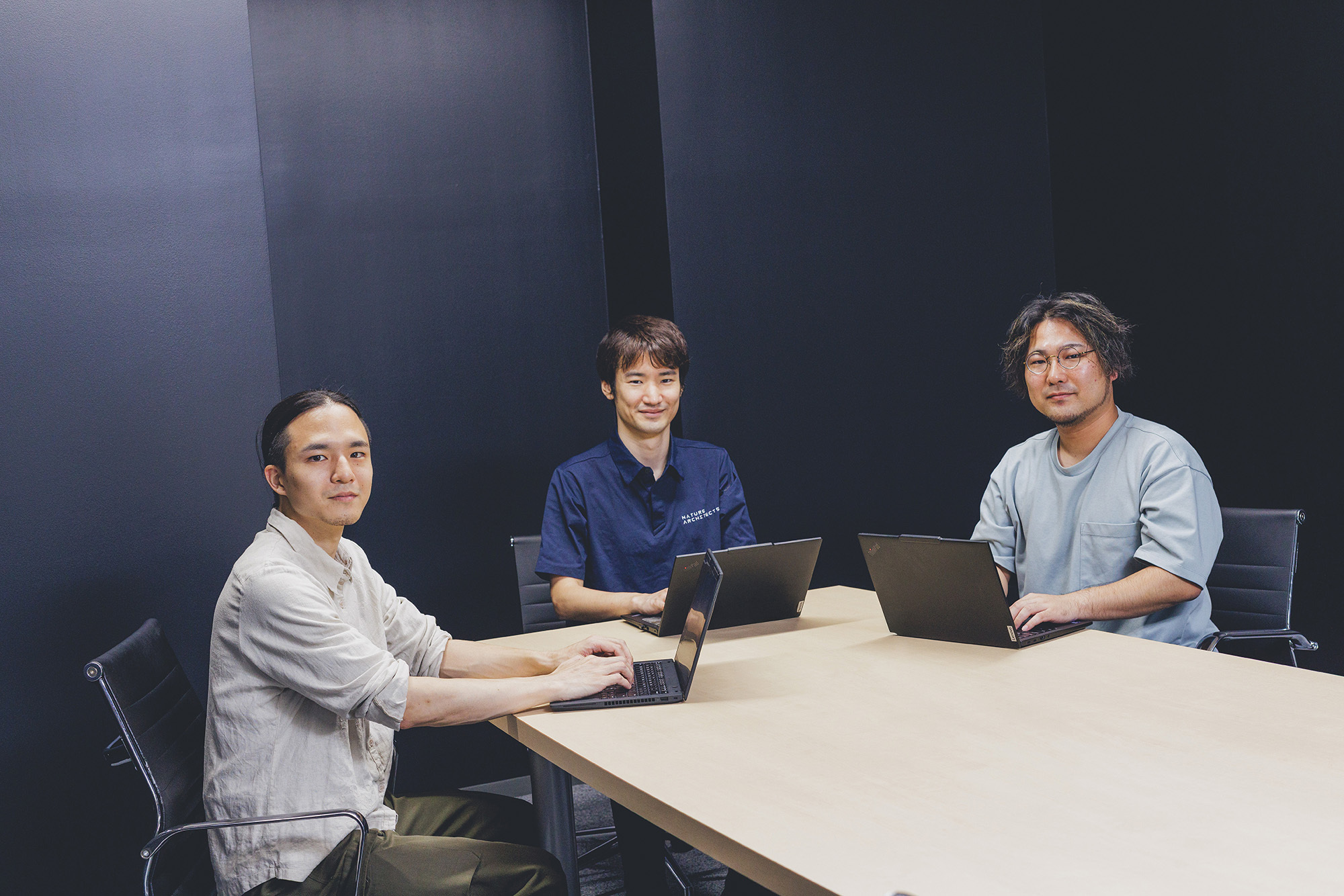高い設計要件に、個の力とチームの力とで向き合える面白さ
PROFILE

夏目 大彰
2020年入社
早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻卒業(修士)。組織建築設計事務所にて教育施設や免震建物、超高層ビルなどの構造設計に従事。業務の傍らコンピュテーショナルな構造設計の普及のためのコミュニティ活動や支援ツールの開発を行う。2020年よりNature Architectsに参画。現在は、クライアントとの共同開発(主に衝撃吸収部材の最適設計、建材の設計)や社内技術開発(社内設計ツールの開発、新技術調査、設計への適用PoC、構造探索)、新しく入ったエンジニアの教育などを担当。一級建築士。
同じ理想を持って、同じようなことをやっている仲間を見つけられた

そして私自身は建築事務所に勤めていましたが、2020年に独立して個人事業主となり、Nature Architectsの仕事も行っていました。そのうちに、ソフトの開発や論文調査など新しい手法を検討しながら設計を行っていく風土に魅力を感じ、2021年に正社員として入社を決めました。
私はもともと、設計の効率や質、コスト面でもより良い設計環境を作っていきたいという理想を持っていましたが、それを社会実装していくにはNature Architectsのアセットを使ったほうが、実現に近づけるとも考えました。
高い設計要件に、個の力とチームの力とで向き合える面白さ
現在は、自動車の防振部材や衝撃吸収部材などの設計を行うほか、設計に使う社内向けソフトウェアの開発、エンジニアの育成・指導などを行っています。部材の設計では、自動車メーカーからの難易度の高い設計要件に対して、ソフトウェアなど設計環境込みで設計していくのが他社との違いであり、Nature Architectsならではの面白さです。難易度の高い設計要件というのは、たとえば、車両が衝突したときの衝撃を半分~3分の1にしたいといったものです。既存の設計の考え方では無理なことも、異なるアプローチで考えられるNature Architectsだから可能にできるのです。
また、その際には個々のエンジニアが考え抜くのに加え、社内で2週間に一度、全体で考える相談会があります。物理、航空・宇宙、家電、数学など多様なバックグラウンドのメンバーがいるので、目からうろこのアイデアをもらえたりするのです。たとえば、Aという設計手法を使ってずっとその設計をしていたが、実は他の業界では同様の場合にBやCという手法を使っていて、そちらのほうが良かった、というようなことが往々にしてあります。いろいろな視点に触れられるのが、面白いですね。
量産品の設計にかかわるという醍醐味

私自身の成長を考えても、前職の構造設計では市販のCADや解析ソフトを使って設計を行ったりしてきましたが、Nature Architectsでは、現場の設計環境をより良くするツールやソフトウェアの開発も行うことができます。これによって設計環境の知見まで身につきます。実際、各々のプロジェクトで作っているツールなどを標準化して、社内に還元することを今、推進しています。
そして、入社後の育成環境としては、Nature Architects独自の1ヵ月間ほどのブートキャンプメニューがあり、Nature Architectsで扱う業界や部材などの概略を掴むことができ、ソフトなどの道具についても身につけられるようにしています。
設計者にとって、より良い設計環境を実現していく

そして、これからジョインしていただく皆さんも、そうした環境づくりについても一緒に考えていくことができますので、より良い設計にチャレンジしたい人と一緒に仕事ができると嬉しいです。また、業界や分野による違いを楽しみ、貪欲に学べる好奇心の強い人は、Nature Architectsにマッチすると思います。興味をもたれたら、ぜひ一度話を聞いてみてください。