大学発の独自の設計技術で、製造業のブレークスルーを支援
2025/10/29
|
-------------------------------------------------------------------- 出典:ビズリーチ掲載記事(2025年9月18日公開)より転載 -------------------------------------------------------------------- |
「あらゆる製造業を設計から革新する」というミッションのもと、製造業に最先端の設計ソリューションを提供するNature Architects株式会社。メタマテリアルや折り紙工学に根ざした独自の「カタチ」を見つけ出す設計技術により、製造業をはじめとするあらゆる企業の商品開発に革新をもたらしています。今急成長中の同社に機械設計エンジニアとして加わる醍醐味について、創業メンバーのお二人に伺いました。
製造業の「限界突破」をかなえる、大学発の独自の設計技術
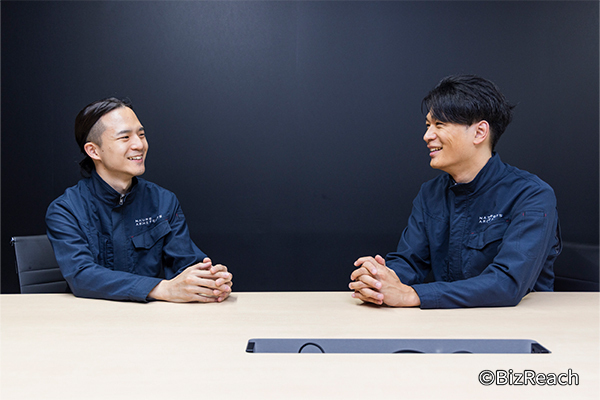
──はじめに、Nature Architectsの創業経緯を教えてください。
須藤:私たちはもともと東京大学大学院で、メタマテリアルや折り紙工学に関する研究をしていました。メタマテリアルとは、材料の特別な形や並べ方によって変形や振動などの物理挙動がコントロールされた構造物です。そして折り紙工学とは、構造(折りのパターン)によって物理挙動を制御する技術を探求する研究分野です。
両者はどちらも「材料に特殊な形状を付与することにより、もとの材料にはない新たな特性を持たせる」点が共通しています。これらの研究に根ざした技術を応用すれば、新たな材料を開発せずとも、従来の何倍もの軽さや耐久性などを実現することが可能になります。
私たちは大学院にいた頃から、この技術に大きな可能性を感じていましたが、当時製造業での活用事例がほとんど見られなかったことから、「この学問を研究室の中だけにとどめておくのは非常にもったいない。自分たちが起業して製造業に技術を提供していくしかない」と思い、2017年に創業に至りました。
──展開している事業とその強みをお聞かせいただけますか。
谷道:当社は製造業のお客様が直面する複雑で難度の高い設計課題に対し、折り紙工学やメタマテリアルの研究成果を基盤とした独自の設計技術を通じて、設計の支援や提案、設計手法の開発などのソリューションを展開しています。現在は自動車業界を中心としつつ、家電メーカーや建設業といった幅広い領域のお客様にサービス提供をしています。
ご相談くださるお客様は、製品を通じて実現したい機能やユーザー体験を明確に思い描きながらも、従来の設計の延長線上では限界を感じているケースが多いです。実際、厳しい市場環境下において、「自社だけでは新しいものが生み出せない」「このままだと事業が立ち行かない」といった深刻な悩みが寄せられています。
そうした課題を解決するうえで、材料を一から開発するのは一つの方法ですが、実用化までに10~15年という長い時間を要してしまうのが一般的です。しかし当社の設計技術を活用すれば、新しい形状により性能を変化させることで、既存の材料を活用したままスピーディに新たな可能性を引き出せます。
須藤:一方、どんなに高い性能を生み出せたとしても、量産化に対応できなければ意味がありません。そのため、私たちはお客様の製造プロセスにも徹底的に寄り添いながら、量産化にも耐えられる設計ソリューションを提供できる体制を整えています。
谷道:まさに、私たちの競争力の源泉は、シミュレーションを活用した独自の設計探索技術にあります。原理原則に基づき、従来の機械工学に閉じない多様なアプローチで網羅的に設計を検討しているため、効率的にアイデアを探索できるのです。
また、設計とシミュレーションを一人の技術者が両方担当し、高速でPDCAサイクルを回しているため、最適解に素早く到達できるのも当社独自の強みです。
大幅な軽量化・コスト削減を実現し、SDGsにも貢献
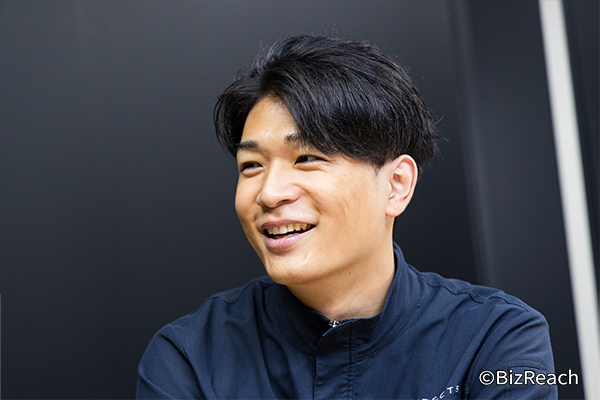
──貴社の技術によって、製造業にどのような変化をもたらせるとお考えでしょうか。
須藤:現在、当社の技術がお客様に大きな価値を生み出している分野の一つが「軽量化」です。自動車業界のお客様であれば、必要な材料の削減によるコスト低減や燃費改善といった成果が期待できます。さらに航空業界においても、燃料消費の削減や座席数の拡大といった形での貢献が可能です。
もちろん、当社が取り組んでいるのは「軽量化」だけではありません。音や振動をコントロールすることで心地よさを向上させ、UX改善にもつなげられます。
こうした技術はあらゆる製造業への応用が可能であり、現在は自動車と航空機の他に、重工業や造船、建築、農機具、ファッション業界の設計にも取り組んでいます。従来の改善では決して到達し得なかったダイナミックな変化を創出できる点に、大きなご期待をいただいています。
近年は環境負荷の低い製品を開発したいという製造業のニーズも高まっており、SDGsの観点から当社の設計技術に関心を持つお客様からのご依頼も増えています。
──非常に革新的な取り組みですね。今後の事業展望についてもお聞かせください。
須藤:創業から4、5年は、私たちの設計技術が「お客様にどうフィットするか」を探索するフェーズでしたが、2023年ごろから急激にニーズが拡大し、今非常に多くのお客様から引き合いをいただいています。このタイミングで採用も強化し、一気に事業拡大を狙いたいと考えています。
私たちが目指すのは、お客様にとっての「エンジニアリング・イノベーションパートナー」です。これからも課題解決に取り組むお客様に伴走しながら、最適な設計を一緒に作り出し、お客様とともに製造業にイノベーションを起こしていくために、今新たな機械設計エンジニアの力を必要としています。
大学の研究室のような「エンジニアの楽園」で課題解決に没頭する

──今回募集する機械設計エンジニアは、どのような業務を担当するのでしょうか。
谷道:商品の全体像を見ながらアイデアを探索することが大切なので、一般的な設計の範囲を超えて幅広い業務を担当してもらいたいと考えています。例えば、形の定義からシミュレーションモデルの構築、有望なアイデアの詳細設計、最適化まで、最終的には一人で担っていただくことを目指します。
担当するプロジェクトは規模も業種もさまざまですが、基本的にその方の得意な技術領域(変形、振動、流体など)が生かせるプロジェクトにアサインするようにしています。まずは経験豊富なエンジニアのサポートとして参加していただき、プロジェクトを回す過程で業務の流れを理解してもらいます。
なお、プロジェクトマネジメントの業務は事業開発のメンバーが担当しているため、エンジニアは設計やシミュレーションなどの自身の業務にしっかりと集中できる環境です。お客様の課題やその解決に向けたアプローチ方法を技術的な観点から明確にすることも重要であるため、特にプロジェクト初期ではお客様と直接会話しながら議論を進めていくことが多いです。
社会貢献の実感を得ながら、技術者としての専門性も高められる
──貴社で働く醍醐味はどういったところなのでしょうか。
谷道:一つは、さまざまな業界・製品・現象を扱える点です。もしメーカーなどで特定の製品を担当する場合、何十年も同じパーツを扱い続けることもめずらしくありません。その点、当社では多様なプロジェクトを経験して知見を広げていけるので、技術者としての知的好奇心が満たされるのは間違いないでしょう。
もう一つ、最先端の設計技術に触れながら、現場が直面している問題を自らの手で解決に導いていける点です。技術だけに没頭していると実課題との距離が生まれてしまいがちですが、当社では技術を追求しながら、社会への貢献実感も得られます。
しかも、私たちが取り組むのはお客様にとって無視できないコアな課題ばかりなので、課題を解く価値や産業へ与えるインパクトが大きく、大きなやりがいを感じられます。
須藤:私も同感です。当社には各社が取り組む機械設計のなかでも、特に難しい課題が集まってくるため、前例のない道を切り開けるのが最大の醍醐味ですね。お客様とともにブレークスルーに近づけたときの喜びはひとしおです。
加えて、当社では「エンジニアの楽園」といえるような、機械設計エンジニアが働きやすい環境作りを目指しています。事業開発のメンバーは全員理系出身で、技術への理解が深いため、ストレスなくコミュニケーションを取ることができます。
また、「研究室制度」といって、勤務時間の2割ほどを割き、興味のある技術をその領域のエキスパートである社員のもとで探求できる制度もあります。専門性の違いはあれど、全員が技術に対して強い興味があり、互いに関心を持ちあう空気が生まれていて、社内のエンジニアからは「大学の研究室のような雰囲気」とよく言われますね。
──機械設計エンジニアとしてどういった方を求めていますか。
谷道:難しい課題に対して、解けない理由を考えるのではなく、どうすれば解けるかを楽しみながら考えられる方です。新しい設計を生み出すためには、人の創造性とコンピュータによる計算(シミュレーション・最適化等)が正しく連携することが重要です。何を計算させるか、計算結果をどう解釈し発想を深めていくかという能力が求められます。
また、「技術に真摯に向き合いたい」という考えの人はフィットしやすいでしょう。当社では、もし誰かが技術的に間違った判断をしていれば、たとえ立場が自分より上であろうと必ず指摘し合える関係性があります。組織のしがらみに翻弄されることなく、誠実に技術を探求したいという考えの方にとって、絶好の環境だと思います。
須藤:付け加えるなら、目の前の業務に没頭するだけでなく、周囲のメンバーの取り組みにも関心を持ち、積極的にコミュニケーションを取る姿勢も大切です。実際の業務において一人で解ける課題はほとんどなく、協力し合うマインドが欠かせません。また、アイデアをどんどん口に出す姿勢も重要ですね。誰かがアイデアを口にしたら、それを一緒になって膨らませる。そんなフットワークの軽さや柔軟さがあると、活躍しやすいでしょう。
少しでも私たちの事業や環境に興味を持ってくださった方は、ぜひご応募ください。設計技術の力で製造業の未来を一緒に切り開いていきましょう。






